【編集部が行く!】安東弘樹&宮島咲良が送る“居心地の良い”時間。bayfm78『MOTIVE!!』インタビュー!(後編)
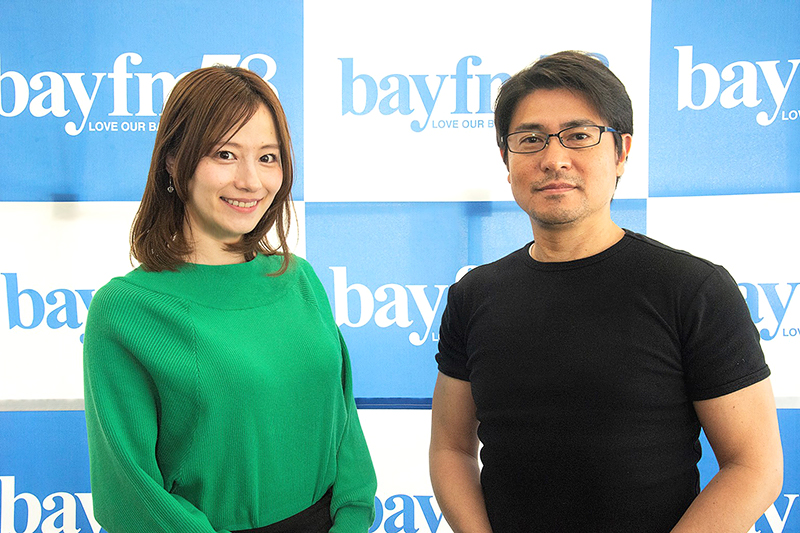
bayfm78で4月より始まった新番組『MOTIVE!!』。初回放送終了後、番組パーソナリティ・安東弘樹さんと宮島咲良さんに、お話を伺ってまいりました。後編では、お2人の考えるラジオの魅力について掘り下げていきます。
ラジオの醍醐味は「1対1の対話」

――お2人は、ラジオに限らず様々なメディアで話されることも多いと思いますが、ラジオに対する印象はいかがですか?
安東:実は僕、ラジオを聴かない人生だったんです。高校・大学の頃は母やきょうだいを養うために働かなければいけなかったので、ラジオを聴く時間も余裕もなかったし、深夜放送を聴いていたら早朝からの仕事ができないので、ラジオに触れる機会がなくて。TBSに入った時、先輩に驚かれましたから。だけどTBSに入って、TBSにラジオがあったおかげで、ラジオの面白さとか、身近さを体感できたのは良かったですね。
東日本大震災が起きた日、最初の大きな地震の3時間後から5時間、生放送を担当しました。CMも音楽もなしで。その中で、例えば「帰宅困難者のために青山学院大学の体育館を開放している」という情報を僕が伝えると、リスナーがTwitterで、「この体育館はパンパンだ」って、僕に教えてくれるわけですよ。それを「すみません。裏を取っていませんが、送ってくれたリスナーの善意を全面的に信用してお話しします。青山学院大学の体育館はもう人が入れない状況とのことです」と、公共の電波で伝えられる。その時に、ラジオの凄さを改めて感じました。今はTwitterも利用者が増えて、古い情報がリツイートされることで、最新の情報がどれか分からなくなるといった問題も起きていますが。
あと、当時TBSを辞めて2年経っていた小林麻耶さん(元TBSアナウンサー。現在は芸能活動を休止中)から、「今、ロケ先の千葉からスタッフと一緒に車で帰っているんですけど、大渋滞でどういう状況か全く分からない。車のテレビを観ても分からないから、TBSラジオを点けたら安東さんの声が聴こえてきて、泣いちゃいました。自分にいろんな情報を教えてくれるみたいで……ラジオってすごいですね」ってメールが来たんですよ。それは日頃、あまり連絡を取っていなかった人たちからも言われて。
東日本大震災の前と後では、僕のラジオに対する姿勢も実は変わっていて。元から真剣に取り組んでいましたが、僕の一言によっていろんな人がいろんな影響を受けるから、より責任をもって話さなきゃいけないなと思ったのと同時に、すごいツールだなとも思ったんですね。
それまでは僕、正直な話をすると「ラジオは生き残っていけるのか?」とさえ思っていました。電波を使ったAMラジオ、FMラジオは未来がないんじゃないかな……ぐらいの。でも、東日本大震災の時に、ラジオは絶対に必要ツールだなと思いました。スマホからラジコで聴いて、もしバッテリーが無くなったら、乾電池で動くポケットラジオで、少なくとも災害が収まるまでは使えて、情報を得られるわけですから。
――手巻きラジオもありますもんね。
安東:おっしゃる通りで。その時に「ラジオは滅ばないな」と感じましたね。

宮島:私がラジオを好きな理由は、やっぱり1対1のツールだからで。大勢に発信することが普通になってきている世の中で、人と人が会話できる唯一のメディアだと思うんです。最近はテレビでもツイートをハッシュタグで拾って紹介したりしていますけど、一方通行なので、対話になっていませんよね。でも、ラジオは対話ができる。
安東:たぶん小林麻耶さんが感じたのはそこだと思うんですよ。僕がテレビで「こちらが○○の情報です」といったところで、メールを送ってくることはなかったでしょう。ラジオだから「ちゃんと一人一人に話しかけてくれている」という気持ちになってくれたのかもしれません。不思議ですよね。たくさんの人に向けて話しているのは、リスナーの皆さんも頭で理解されているとは思うのですが。
宮島:しゃべっている私たちも、言葉の選び方から変わりますね。そこが人間性の目立つラジオの特徴だと思うんですよ。人それぞれ差はありますけど、アナウンサーに限定したら、ラジオがある局とない局で、人としての奥深さみたいなものが違う気はします。テレビが良い悪いという意味ではなく。
あと、ラジオってある程度、知識があって、自分の意志がしっかりしていないと務まらないと思うんです。当たり障りのないことばかりいっていると、成立しないじゃないですか。聴いている人もそうだと思うんですよね。今日もコメントをTwitterで見ていたら、「一緒に考えられて面白かった」とか、「気づいていなかったけど、そういえばそうでした」っていう感想をいただいていて。一緒に考えられることが、ラジオの醍醐味だと思うんです。
安東:そう考えると、FMっぽくない番組ですね。
宮島:そうなんですよ。2人ともAM局出身なので、結果AMラジオみたいになっちゃったんですけど。爽やかな金曜午前の番組を目指すなら、たぶん私たちは呼ばれてないと思うので(笑)。それが良い方に出ていたらいいなと。
無理をせず長く続く番組に

――ラジコだとAMもFMも横一列に表示されますから、聴く側としては違和感がなかったかもしれませんね。では最後に、この番組を長く続けるための秘策はありますか?
安東:無理をしないことですかね。やっぱり良い番組って、風通しがいいですよね。話し手とスタッフの。遠慮をしだしたら末期だと思うんですよ。
例えば今日、困ったことはないし、スタッフの皆さんへの注文も一切ないんですけど、逆にどんどん言ってほしいです。たぶん、探り探り無理をしないで、宮島さんに頼ってやっていくしかないな、ぐらいに思っているので。今は宮島さんから褒められていますけど、いつか「チッ」と思われるときも来るかもしれないじゃないですか。
宮島:すぐ言います。すぐ言いますね、そうなったら。
安東:本当にお願いします。僕からは言えないかもしれないですけど。
宮島:言ってください。それは言ってください、本当に。
安東:そうやって全員が無理しないでっていうのが、長く続くことにつながるのかなという気がします。宮島さんはどうですか?
宮島:うーん、分からないですけど「しゃべるのを辞めないことかな」と思って。私がKBC九州朝日放送を退社するときに、大先輩の沢田幸二アナウンサー(※)から、「何があってもしゃべりは辞めないでください」って言葉をいただいたんです。決して怒らない方で、ラジオではあんなに饒舌なんですけど、普段は言葉数が多くはないんですよ。そういう方が見ていてくださっていたのが、私の原動力になっています。
「こう言われたんです!感動したんです!」ではなく、スッと「あ、分かりました。(しゃべりを)辞めないです」と、自分の中で納得できたので。だから長く聴いて頂くには、とにかくしゃべり続けることですかね。安東さんと同じようなことを、ニュアンスを変えていっただけな気がしますけど(笑)。
安東:という感じで、「無理をしない」コンビということで、よろしくお願いします(笑)。
――ありがとうございました。これからも、お2人の息の合ったコンビネーション、楽しみにしております!
(※)さわだ こうじ KBC九州朝日放送のエグゼクティブアナウンサー。1983年~1990年まで放送された夜ワイド『PAO〜N ぼくらラジオ異星人』で当時の若者から絶大な支持を得る。現在はテレビ『サワダデース』、ラジオ『PAO〜N』『DJサワダデス』を担当。『PAO〜N』で披露する早口オープニング(通称“前ピン”)は、爆笑問題・太田光氏も絶賛している。
- MOTIVE!!
- 放送局:BAYFM78
- 放送日時:毎週金曜 9時00分~13時00分
- 出演者:安東弘樹、宮島咲良
-
公式Twitter
※放送情報は変更となる場合があります。
【パーソナリティプロフィール】
安東弘樹(あんどう ひろき)
1967年、神奈川県生まれ。1991年、TBSにアナウンサーとして入社。テレビ、ラジオで多くの番組に出演。2018年3月に退社し、フリーに。多趣味で、中でも車に関しては日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考委員も務めるほど
宮島咲良(みやじま さくら)
1983年、東京都生まれ。2007年、アナウンサーとしてKBC九州朝日放送に入社。2010年に退社してフリーに。華やかな容姿とは裏腹なオタク気質で、大のスーパー戦隊好き
ラジコでラジオを聴こう!
▼スマートフォンで聴くなら
http://m.onelink.me/9bdb4fb
▼パソコンで聴くなら
http://radiko.jp/

