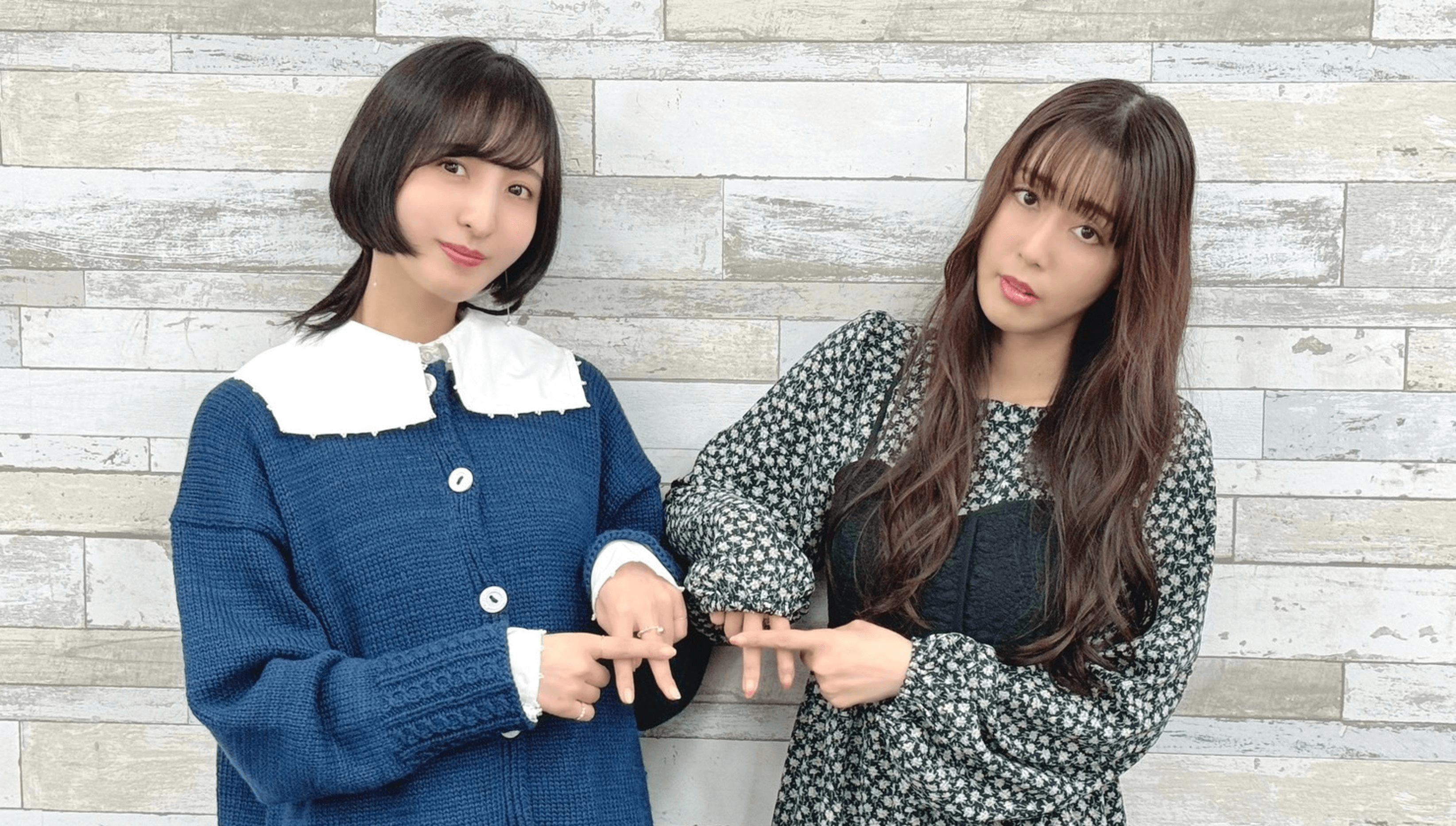宇多丸、『あの頃。 』を語る!【映画評書き起こし】
ライムスター宇多丸がお送りする、カルチャーキュレーション番組、TBSラジオ「アフター6ジャンクション」。月~金曜18時より3時間の生放送。
『アフター6ジャンクション』の看板コーナー「週刊映画時評ムービーウォッチメン」。ライムスター宇多丸が毎週ランダムに決まった映画を自腹で鑑賞し、生放送で評論します。
今週評論した映画は、『あの頃。』(2021年2月19日公開)です。

宇多丸:
さあ、ここからは私、宇多丸が、ランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する、週刊映画時評ムービーウォッチメン。今夜扱うのは、2月19日から劇場公開されているこの作品、『あの頃。』。
(松浦亜弥『桃色片想い』が流れる)
……すげえ曲だよな、これな。はい。劔樹人さんの自伝的コミックエッセイ『あの頃。男子かしまし物語』を松坂桃李主演で映像化した、大人の青春物語。うだつの上がらない生活を送っていた劔は、松浦亜弥が『桃色片想い』を歌う姿を見て、ハロー!プロジェクトのアイドルに夢中になる。やがて個性豊かな「ハロプロあべの支部」の面々たちと知り合った劔は、くだらなくも愛おしい青春の日々を謳歌するのだが……ということでございます。松坂桃李の他、仲野太賀や山中崇、若葉竜也さんなどがハロヲタを熱演。あと、ロッチのコカドケンタロウさんが、後に赤犬のボーカルとなるイトウことタカ・タカアキさんを演じられております。監督は、『愛がなんだ』の今泉力哉さんが務めた、ということです。
ということで、この『あの頃。』をもう見たよ、というリスナーのみなさま、<ウォッチメン>からの監視報告(感想)をメールでいただいております。ありがとうございます。メールの量は「めちゃ多い」。出ました、今年最多!ということでございます。賛否の比率は、褒めの意見が7割弱。褒める意見として多かったのは、「ハロプロ好きだったので当時のことが懐かしく、またディテールの再現度にも驚いた」「アイドル好きに限らず、何かに猛烈にのめり込んだことがある人には刺さる」とか、「過去を懐かしむのでなく、今を肯定するメッセージが素晴らしい」「俳優陣はみんないいが、中でも仲野太賀がよかった」などがございました。(仲野太賀さんが)絶好調ですね。
一方、「ストーリーが貧弱。後半から退屈してしまった」とか「『あの頃。』の日々が全然楽しそうじゃなく、羨ましくもない」「ホモソーシャルな描写が強すぎて抵抗があった」などの批判の声もありました。これ、なかなか重要な指摘もあるので、後ほどしっかりと紹介しますね。
■「何かに夢中になったことがある人なら誰にでも共感できるであろう作品」byリスナー
まずはよかったという方のメール。もうすごいいっぱい来ててね、ちょっと紹介しきれない。
ラジオネーム「スルッテート」さん。「映画『あの頃。』、見ました。これは“バラ色の人生”を描いたものでも、“花束みたいな恋愛”を描いたものでもなく、まさにアイドルへの“桃色の片想い”を捧げるオタたちの遅れてきた青春を描いた物語でした。切り口こそハロプロですが、今泉監督はオタを好奇な目で描くことがなく、何かに夢中になったことがある人なら誰にでも共感できるであろう作品として昇華させていました。個人的にこの作品がうまく行ったのには、今泉監督自身があまりハロプロに関心がなかったというのが大きかったように思います。ひとつは松浦亜弥の描写。これはハロプロが好きすぎると、アイドルに敬意を払いすぎて『松浦亜弥を見せない』という手段を取ったように思いますが……」。
たしかにね。(顔などは直接には)「見せない」っていう見せ方もあったけども。「……BEYOOOOONDSの山﨑夢羽さんを起用し、正面突破を図りました。それにより、モニターを通して見るあやや。そして主人公が実際に見るあややと違いを出すと思い切った描写にし、観客がモヤモヤすることなく映画として成立させていたように思いました」。あと、山崎さんのやっぱり、あの首の角度とか、声の発声とか、もう完コピぶりもすごかったですよね。あと、いろいろと書いていただいて。「ご本人登場とかをしなかったのもよかった。他にも演技のアンサンブルの見事さなど、書きたいことがありますが、そこはお任せします」というあたり。
あと、ラジオネーム「きんぴかごぼう」さん。この方は53歳女性。「大人になっても夢中になるものがあって、一緒に盛り上げる仲間がいる彼らが羨ましくなりました。中2の放課後男子のような狭い部屋でのワチャワチャはとてもリアリティーがあり、1人1人が個性的で、劔はもちろん特にコズミン役の仲野太賀さんの演技がダメ人間を愛されキャラとする演技で引き込まれました。きっと今でも『あいつ、最低だったよな』と笑いながら言われている様子が想像できます」とか、ありました。
あと、非常に本当にご自分の、自分史というかね、そこと重ねて語っていただくメールも多くて。ちょっと全部紹介しきれないのですが、ラジオネーム「カルメン(オーイェーズ)」さん。初めてメールをいただきましたけども。この方はやはり、ヲタ友達がちょっといろいろと病気にかかられてしまって、非常に劇中と似た展開があった、という思い出を書いていただいたりとか。「ゆき」さんという30代女性の方もですね、やっぱりつらかった時に支えになってくれたのがハロプロだった思い出というのを、重ねて、非常にいろいろ書いていただいて。熱いメールでございます。ありがとうございます。
一方ですね、ちょっと批判的なメールもがっつりと紹介したいんですよね。ラジオネーム「にごう」さん。「『あの頃。』、ウォッチしてきました。賛否で言うと否です。ホモソーシャルで露悪的で、開き直りきったようなオタクイキリがきつく、そこを自覚的に見る視点がゼロではないにしても、とても類型的な描写で、最終的にはかつて所属していたコミュニティの総括を“モラトリアムからの卒業”的な生ぬるい感じで済ましていることに、『今の時代にこういうコミュニティを題材に選んで、そこか?』というがっかり感がありました」というね。
「彼らにとってはアイドルやハロプロよりも、仲間内での“このノリ”を共有するための媒介の方が大事なんだと思いました。それを象徴しているのが、とあるイベントのシーンの描写で」という。非常にこれはよろしくないというか、非常に不快であるというか、たしかに全然よろしくないことが描かれてるんですけど。「『彼女を寝取る』という発言や、それをネタにすることそのものが最悪ですし、潜在的なミソジニーやインセル的マッチョイズムをものすごく感じますが、私もアイドルファンなので、映像に映されている石川梨華さんの感動的シーンよりもそっち(仲間内でキャッキャキャッキャやる方)を楽しんじゃうんだ……と思ってしまいました」というね。
それで本当になかなか鋭い指摘があって。「アイドルがコミュニケーションの媒介になること自体は私も肯定します」と仰っていつつ、あと、彼らがなんでもかんでも面白おかしく解釈しようとするその背景みたいなものにも一定の理解を示しつつも、「でも、やっぱり彼らはそのために、自分たちの物差しで他者をジャッジし、いろんな他者を消費しているじゃないか。その行為の結果や対象に向き合わず、その暴力性にも気付かず、関係性や立場がごく自然な時の経過とともに変化しただけで、『もう戻れないあの頃』としてノスタルジックに終わったものにしてしまうことが全く信用できませんでした」と。
で、やっぱり最後の方の展開で、その仲間を明るく……その仲間内のノリというところに、やっぱり女性というものを介して面白おかしくしていくという感じが、非常にマッチョな価値観で嫌だ、ということも書いていただきつつ。あと、道重さゆみさんの引用についても「最後、道重さゆみさんの言葉が引用されますが、不適当な引用だなと思います。彼女の『常にピーク』という言葉の重みは、常に他者の物差しで自分の『かわいい』がジャッジされることを拒絶し、自分のかわいいを自分で肯定し続けてきたからこそ生まれるものです。そして30歳になり、今度は『年齢』という世間一般の物差しでかわいいをジャッジされることをも拒絶する。だからかっこいいのです。
対して、主人公の『今が一番楽しい』はどういう意味でしょうか? ずっと物事を面白おかしく消費する側で、でも今は社会的基準でも順当なステップアップを遂げている彼に『今が一番楽しい』と言われても、『そうでしょうね』としか思えませんでした。乱暴なことを言いますが、この映画を楽しめるのは、彼らのように消費する側の安全地帯に立てていた人だけで、彼らのようなコミュニティーに消費される側だったり、消耗された経験があったりする人には楽しめないのではないかと思いました。正直、私はこの映画での『もう戻れないあの頃』より、今なお決して変わらず存在する地獄ばかり見出してしまいました。見ていてとてもつらかったです」という。
これ、だからすごく「ああ、なるほど」というか。結構頷ける指摘もあるし。すごくこの作品に対していい解釈をするならば、要するにその、ある人物のものすごく嫌な一面っていうのも……すごく嫌な人でもあるよね、という見方。という風にも響く映画でもある、っていうかね。両面があることを描いてる映画だ、ということが言えるのかもしれないですけどね。でもちょっと、なかなかスルーし難い重要な指摘だと思ったので、ご紹介させていただきました。
ということで、メールありがとうございました。皆さん。本当に熱量があるメールでございました。
■原作は、モーヲタを描いた劔樹人さんの自伝漫画『あの頃。男子かしまし物語』
ということで、私も『あの頃。』、TOHOシネマズ六本木で2回、見てまいりました。入りはまあまあと言ったところでしたけど、男女比、年齢分布ともにですね、ジャンル的に特定をしづらいという感じが、非常に印象的でしたけどね。ということでまあ、モーヲタ・シーンを描いた云々に関しては、もう番組オープニングでもお話しましたので。みやーんさんの公式書き起こしもぜひ、そこからもお願いします、という(笑)。ごめんね、みやーんさん。手間を増やしてね。(編註:下に付記してあります)
で、ですね。原作があるわけですね。非常に奇妙極まりない映画企画、これがなぜ成立したのかっていうと、まずは劔樹人さんによる原作漫画というのがある。『あの頃。男子かしまし物語』というのが、2014年にイースト・プレスから出ていて。これ、漫画と文章が一緒になった……ご本人もあとがきで書かれてますけれども、杉作J太郎さんの一連の作品、特に『ヤボテンとマシュマロ』とかあたりですかね。それに近いスタイルですね。それで実際に僕、最初にこの『あの頃。』という原作本を読んだ時に感じたのは、「ああ、これは俺らの世代にとっての『卒業― さらば、ワイルドターキーメン』なのかな」っていう。これ、杉作J太郎さんの素晴らしい青春漫画なんですけども。
まあ、今回の映画でもね、松坂桃李さん、(杉作さん率いる)「男の墓場プロダクション」のTシャツやらバッジやらを身に着けていらっしゃいましたしね(笑)。あれはたぶん、劔さんの私物なんでしょうね。というか、衣装とかグッズなど、今回の映画ではかなり、実際のホンモノを用意しているあたり、すごくちゃんとしているあたりでございます。
とにかくその、劔さん。人生で非常に落ち込んでいた時期にあややに救われ、一生の仲間たちができた、みたいな、そういう話。自伝的エッセイ漫画というのが2014年に出て。まあ、この本が出たこと自体、我々的にはですね、「ええっ? モーヲタの本を出すの? モーニング(本体について)じゃなくて、モーヲタの本を出すんだ?」みたいな。あ、ちなみに今日は、当時まだ「ハロヲタ」という言葉はなかったので、「モーヲタ」で統一をさせていただきますが。非常に驚きをもって読んだわけですけども。
ちなみに劔さん。もちろんね、(バンド)「あらかじめ決められた恋人たちへ」のベーシストにして、今は犬山紙子さんのダンナさんとしても非常に知られていますが、どんな人かというのを知りたければ、一番手っ取り早いのは、入江悠監督の2011年の作品『神聖かまってちゃん』。これは僕、2011年5月15日に評しましたけど。
当時、かまってちゃんのマネージャーだった劔さん、実質これ、主役なんで。劔さんがいかにかわいらしい人柄か、あと、たたずまいとかね。もうルックスも含めてめっちゃかわいいので、ご存知ない方はですね、ぜひご確認いただきたいんですけどね。だから松坂桃李さんが、あのキュートさをちゃんと再現できるのか?っていうのがポイントだったんですけども。まあ見事なものでございましたけどもね。松坂さんもね。
■監督は、「コミュニケーション下手な挙動不審男子」の機微を切りとるのが上手い今泉力哉監督
で、とにかく劔さんの自伝的原作。インタビューなどによれば、2015年ぐらいから既に映画化の話が出ていたということで。これ、人脈的に考えると、これを映画化するという時はですね、劇中にも出てきたロビンさんとか、あと、今回の映画版では完全にオミットされていましたけども、リシュウさんとか、そして後にタカ・タカアキさんという、要するに赤犬の新ボーカルとなっていくイトウさんというあのキャラクターであるとか……要するに赤犬という素晴らしいバンドがいて、その赤犬ともつながりの深い山下敦弘さんあたりが、映画化をするとなると適任なのかな、順当なのかなって、実は僕、勝手に想像をしていたんですけども。
実際に監督として白羽の矢が立ったのは、山下敦弘さんのさらに下の世代というか、まあ師事されてたこともありますよね、山下さんにね。2019年、ご存知『愛がなんだ』で本格大ヒットを飛ばしました、今泉力哉さんでございます。当番組的にはですね、昨年5月26日に、「映画の音声ガイド」特集に、松田高加子さん、そして黒澤美花さんと共に、リモートでご出演いただきました。「公園からリモートしています」なんて仰っていましたけども(笑)。
それで、たしかに今泉監督、パンフレットに南波一海さんが寄稿されているコラムでも南波さんが仰られているように、要は「好き」という、この得体の知れない情動、理屈では割り切れないもの、それが巻き起こす日常の中の、人と人との間のざわめき、っていうのを、見事にすくい取る名手であって。その意味で、ハロプロという「好き」を見つけたことで人生が輝き出した人々……その1個1個は実に他愛もない、なんならしょうもないエピソードの連なりから、なにかかけがえのない人生のある一時期のようなものが浮かび上がる、という、この劔さんの原作の本質とすごい合っているわけでね。今泉さんのモチーフというか、スタンスみたいなものが。
あと今泉さんは、「恋愛映画の名手」みたいな言い方をされるけども、一方で、コミュニケーション下手な挙動不審男子っていうか(笑)、その、褒められたもんじゃない男性性も含めたですね、挙動不審男子。そういう男の機微みたいなものを切り取るのも、実はめちゃめちゃ上手くて。たとえば、2013年の『サッドティー』であるとか、2017年の『退屈な日々にさようならを』とか、このあたりにもそういう要素があったりもするんだけども。
この後、4月にようやく公開となる『街の上で』という作品。こちらはですね、今回西野さん役を熱演しておりました、若葉竜也さん主演。あと、萩原みのりさんがまたピリリと印象を残す好演ぶりを見せていますが。この『街の上で』。これがなかなかの傑作っていうか、僕はこれ、すでに大好きな1本になっちゃってるので。これ、公開タイミングでガチャをぜひ当てたいな、当たるといいなと思いますけども。とにかくその『街の上で』と今回の『あの頃。』は、特にその今泉監督の、さっきも言ったようにコミュニケーション下手……下手したら、傍から見たら挙動不審なボンクラ男子の右往左往を、何とも愛おしく切り取った、一種の連作的な共通性も感じさせるような二作になっているかな、と思います。
■「好き」が生まれたことが、誰かの人生に火を灯した瞬間を丁寧に捉えてみせる
というわけで、『あの頃。』の映画化、実は非常にドンピシャになっている今泉力哉監督というのと、さらに今回、座組的に面白いのはですね、冨永昌敬監督ですね。『乱暴と待機』とか、僕が大好きな『ローリング』とか、その冨永さんが、珍しく脚本のみで参加している。冨永さんご自身の監督作で言えば、2018年のあの『素敵なダイナマイトスキャンダル』。末井昭さんの……実在の人物、事象が多数登場する、自伝的群像劇であり、それぞれは散文的なエピソードの連なりを1本の映画として再構築してみせる作品として、今回の『あの頃。』に通じるものがあるのは、この『素敵なダイナマイトスキャンダル』かな、と思いますけども。
いずれにせよ、今回の脚本の冨永昌敬さんにせよ、監督の今泉力哉さんにせよ、これはさっきのメールにもあった通りですね。劔さんとか、後に「恋愛研究会」と名乗っていくあの面々であるとか、あるいはその当時のモーヲタ・シーンというものに対して、いい意味で距離があるからこそ……距離があるからこそ、敬意を持って、きっちり取材などを重ねて作品に落とし込んでいく、ということもしている一方で、過度のセンチメンタリズムとか、逆にその自意識過剰の照れによる露悪、などに陥ることなく、言っちゃえば、結構フェアな視点というかな、フラットな視点で……というのを本作に対して保つことができている、っていうあたりがプラスかな、という風に思います。
たとえば、やっぱり最大の焦点。この原作を映画化するにあたっての一番の焦点は、「アイドルファン」というものをどう描くか?っていうところですよね。これ、これまでの映画化とかドラマの作品ではですね、アイドルファンというものが出てくる時っていうのは、9割方というか、99パーセントは、全く理解も敬意もない、記号的な茶化しとして出てくることが、ほぼほぼ全部だったわけですね。もう、そんなのしかなかったわけですよ。しかし本作『あの頃。』はですね、さすが今泉力哉監督作というべきでしょうかね。「好き」という情動のその発露がですね、人生をちょっぴり、ちょっとだけ輝かせて、それでその自分の世界を広げてくれる、ということを、まずはしっかり丁寧にすくい上げて見せる、っていうことですね。
たとえば、先ほどオープニングでも山本さんとチラリと言いましたけども、序盤。松坂桃李さん演じる劔青年の、見事に最初、目の光、瞳から光が、消えてるわけです。死んだ目なわけですよ。それが、その冷めきったお弁当と同じように冷めきった目をしたその劔青年の目がですね、その名曲中の名曲『桃色片想い』、松浦亜弥さんのミュージックビデオをボーッと眺めるうちに、みるみる涙でいっぱいになり、そして輝きを取り戻していく。つまり、「好き」が生まれたことが、誰かの人生に火を灯した瞬間、というのを、この映画は、まさに映画だからこそ目撃して記録すべきものとして、まずは本当にじっくりと、丁寧に捉えてみせる。これは要するに、劔さんの原作でもできないことですから。実際、その瞬間をドキュメンタリックに捉えるということは。そしてまた、それに応えてみせた松坂桃李さんの見事な演技、ってことですよね。
そしてまた、そうやって心に灯った「好き」の熱がですね、同じ「好き」を抱えた他者によって、「お前も熱っぽいけど……その『好き』に、お前もかかってるんだろ?」って、感知されるし。あるいはこちら側も「あっ、あなたもこの熱、俺と同じ『好き』の熱だ!」ってことで、シンクロしていく。要は、自分の「好き」が他者と共有された、という、これは言っちゃえば、自分がずっと抱えてきた孤独っていうのが他者と共鳴した喜び、という言い方すらできることであって。それによって、閉じていた自分の世界が、どんどん開かれて、広がっていく。まあそんな「好き」の波及効果っていう面も、この作品は、ユーモアに包んではいるけども、茶化したり見下すことなく見つめてみせている、という風に思います。
■「好き」というものの諸相を、いい面、悪い面、美しい面、変な面、そのいろいろを描いていく
これ、実際に本当に、当時のモーヲタシーンっていうのは、まるで秘密結社のように、『ファイト・クラブ』のように、本当にそこでどんどんどんどんいろいろな人が……全く立場も、たとえば社会的地位も違う人同士が繋がって、それで今も友人である、っていう。これは全く僕らも同じですからね。しかし、それと同時にですね、決して過剰に美化などもしない。自分の「好き」っていうのが、でもそれは傍から見ると歪なものだったり、ドン引きされたり、社会的には肩身の狭いというか、認め難いものだったりする、っていうことも、これは今泉力哉監督、これまでの恋愛映画とかでもね、冷徹に描いてきた部分ですよね。「あなたのその『好き』、ちょっとおかしいよ?」っていうのは。
たとえばその本作の主人公たち、あるいはそのイベントやコンサートに集まるヲタたちっていうのは、それぞれ間違いなく、当人たちにとっての切実な「好き」っていうのに突き動かされた、一応純粋な熱の発露をしているんだけども、でも、一歩引いた赤の他人の目線から見ると、やっぱりそれは引く人は引きますよね、っていうか。まあ、それも無理からぬものですよね、っていうようにも描いている。
というような視点も、やっぱりそれはユーモアにはくるんでいるんだけども、ただそのヲタのもののあり方全体を見下したりバカにするのとも違う、やっぱりある種のフェアさっていうのをキープしながら、進んでいくわけですね。で、先ほども言いましたけども、その学園祭で、たとえばモーヲタ・トークライブイベントを開催して、「大盛況ではあるんだけど、傍から見るとこうだぞ?」みたいな。あれはちょっと、僕は自分を見るようで、頭を抱えてしまった瞬間ではありましたけど(笑)。
あと、本作で非常に重要なポイントは、モーヲタたちの応援スタンス……要はですね、疑似恋愛対象としてだけがアイドルファンのあり方ではないというか。それだけが……まあ、それが好きな人もいるけど。少なくとも当時、2000年代初頭に盛り上がっていたモーヲタ・シーンっていうのは、劇中の彼らのように、たとえば独自でイベントを開いたり、その中でああだこうだと議論をしあったり……僕個人はどちらかというと、ひいきの野球チームを応援する、というのに近い盛り上がりを見せていて。つまりその、モーヲタとかアイドルファンの非疑似恋愛的側面というのをやっぱりきっちり押さえてる、っていうのも、実はこれ、映像作品で描かれたアイドルファン像としては、非常に画期的なものだったかな、という風にも思います。やっぱりちゃんと直接、当事者がやってるだけのことはある。
というわけで、今泉力哉作品的に、「好き」というものの諸相を、いい面、悪い面、美しい面、変な面、みたいな、そのいろいろを描きつつ、今回はアイドルファン、初期モーヲタという立場を通して、時に愛らしく。そして時にグロテスクに……しかしトータルではやはり、その忘れがたい人生の一局面、否定はしがたい人生の一局面として描き出してみせる、というこの『あの頃。』という作品。ネタバレしないようにある程度、伏せながら話しますけど。
■「好き」がある人生っていうのは、やっぱりそれだけで素敵じゃないか
仲野太賀さん演じるそのコズミン。まあ、本物はコツリンさんですけども。いかにそのセコい最低の人物かっていうのを(笑)散々描いておいてから……とはいえ、たとえば中盤の名シーン、先ほどもチラリと言いました。将来に不安を感じ、あややのポスターを剥がしかけるほどにまたまた落ち込んでいた、その松坂桃李さん演じる劔さんを励ますべく、シチューを作ってあげるコズミン。そこに届く一封の封筒、そしてシチューの本当のお味とは……という。これ、松坂さん、太賀さん、ご両者のアドリブも非常に存分に活かされた、というこの名シーンなどもあって、要は本当に生きた人間として作品中に息づいている、このたとえばコズミン。「最低だな、あいつ」っていうのを、(観客である)俺らも「最低だけどまあ、でも優しいところもあるんだよな」みたいなことを、生きた人間として感じるような。
その彼がですね、非常に大きな人生の岐路を迎えるわけですね。その現実を目の当たりにした時の、その太賀さんの、目の演技がすごいです。それもちょっとぜひ堪能していただきたいのですが。とにかく、これは下手な監督とか、あるいは志の低い作り手がやればですね、目も当てられないことになりかねない、愁嘆場ばかりになってしまいそうな後半の展開をですね、しかしこの『あの頃。』という作品は、やはり絶妙な距離と温度感で、いい人なんかじゃない、むしろ最低な人の人生……ドラマや映画、なんなら我々自身も赤の他人に対してなら、無視したり、軽視したり、批判したりするかもしれない、そんな人の人生の、「でも、それだってかけがえないだろう?」っていう、かけがえなさ、愛しさを、まさに目をそらさずに差し出して見せる、というか、映し出して見せる、というところに価値があるかなと思います。
「好き」がある人生っていうのは、やっぱりそれだけで素敵じゃないか、というようなことですね。そして、その「好き」そのものは変質したとしても、その先にある自分の人生っていうのも、やっぱりまた素敵じゃん、っていうことだと思うんですけどね。ということで、キャスト1人1人の素晴らしさにちょっと触れている時間がなくて申し訳ないですが。やっぱりこれ、松坂桃李さんがこの役を受けたからこそ成立した企画でしょうし。もう松坂さんのことはいくら讃えても讃えるすぎることはないと思います。あと、長谷川白紙さんによる劇伴。これまた適度な温度感、距離感を保っていて、非常にかっこいい上にクールで、よかったと思います。
■「ああ、モーヲタで自分もよかったな」って思うような1本
ただですね、先ほどの批判メールにもあった通り、正直やっぱり彼ら。恋愛研究会の、あのすごくホモソというか……まさにホモソ!という感じのノリは、たとえば東京で僕らがRECとキャッキャやってたノリともまた全然違うもので。正直、あの壇上でやる、彼女を寝取った、寝取らないとか、そのノリは正直、俺がもし自分らのイベントでやったら、それはやめろ!っていうことに当然なるぐらい、それは本当にドン引きする……まあ、その良し悪しをジャッジする場面でもないとは思いますけどね。ただ、そこはやっぱり嫌悪感の方が先に立っちゃう人がいるのは当然だと思うし。
あと、そこも含めたイベントシーンですね。要するに、部屋でワチャワチャやっているシーンは皆さん、演技達者だからいいんだけど、客を前にしたトークイベントっていうのの、ああいう面白さみたいのは、ちょっとこれ、劇中で再現するのは難しいところなのかな、それゆえになんか構造のヤダみみたいなものだけが先に立っちゃう部分がちょっとあるのかな、っていうのは……「ああ、ここは再現、難しいんだ。これだけの芸達者をもってしても」っていうのは、ちょっと思ったりしましたね。
ということで、さっきからね、「距離感とか温度感が素晴らしい」とか言って、僕自身が全く距離を取れてない評で申し訳ございませんでしたが。でも僕自身はやっぱり、「ああ、モーヲタで自分もよかったな」って思うような、「RECたちとまた飲みたいな」という風に思うような、そんな1本でもありました。あと劔さんとも飲みたいな。ロビンさんとも飲みたいな、西野さん、元気かな、とか思うような作品でもございました。全然距離が取れていなくてごめんね。ぜひぜひウォッチしてください!
【補足1】番組オープニングゾーンにて
宇多丸:……さて、そんな私が本日、ムービーウォッチメンで扱いますのは、今泉力哉監督、そして原作は劔樹人さんのエッセイ漫画というか、自伝的漫画エッセイというか、『あの頃。』というね、元の本は『あの頃。男子かしまし物語』というのが付いてますが、これの実写映画化版。劔さんを演じるのは松坂桃李さんということになっておりますが。
山本:これ、要するにアイドルに夢中になる大人の青春物語というようなことですかね。
宇多丸:そうですね。要するに劔さんをモデルにした、その松坂桃李さんの演じる主人公が、バンドをやってるんですけど。ベーシストなんですね。劔さんもベーシストで。なんですけども、なかなかいろんなことがうまくいかなくて、本当に気分的に落ち込んで……これ、実際の劔さんもそうだった時に、友人からふともらった松浦亜弥さんのミュージックビデオ。これを見ているうちに、ぽろぽろと涙が流れて……っていう。これも本当にあったことで。そこから、だんだん知り合った仲間たちとイベントをやったりとか、いろんなことをやったりして、キャッキャキャッキャとやってる日々。でも、その日々も永遠には続かず……というような話ですね。山本さんもご覧になって?
山本:見ました見ました。なんだろうな、とにかくざっくりとした感想を言いますと、すごく最後は切なく悲しくキューッと締め付けられる思いと同時に、なんかあったかい気持ちになったんですよね。それで映画館を出た後に、人が楽しそうに笑っている姿とか、友達同士でキャッキャしているのを見ると、すごく優しい気持ちになるような……。
宇多丸:本当にどうしようもない人たちですけどもね。先に言っておきます。もう、主人公たちを含めて……これ、「アイドルファンだからどうしようもない」っていうんじゃなくて、アイドルファンがダメなんじゃなくて、あんたらがダメなんだ!っていう(笑)。本っ当にどうしようもない……これ、全然褒められたもんじゃないどうしようもなさも含む、どうしようもない人たちで。なおかつこれ、完全に我々も知り合いというか、知人だったり、友人だったりする人たちをモデルにした人物だったりするんでね。俺、でも出会う前なんで。「こんなことやってたの? バカじゃない? なにやってんの?」みたいなのはちょっとありましたけどね(笑)。
山本:でも、その輪の中で楽しいことっていうのはやっぱりみんなあるよなっていうのは……。
宇多丸:そうね。あとやっぱりさ、これはちょっと後ほどもネタバレしないような感じで言いますけど、本当にほら、「あいつ、最低だよねあいつ、本当に人としてマジでどうかと思うわ……」っていう人の人生っていうか。映画とか、もちろん他人の人生だったら、そういうしょうもないあれだったらまあ軽視したりとか、無視したりとか、批判したりとか、っていうことはあるけども。でも、そういう「あいつ、本当にどうしようもないよな」って言ってゲラゲラ笑って思い出すみたいな。これってなんか、やっぱり我々の実人生は、むしろそっちの方が本当っぽいよね、っていうかさ。要するに、いい人としてみんな死んでいくわけじゃないっていうか……あ、「死ぬ」って言っちゃった。まあいいや。そんなようなことがあったりしますよね。
山本:はい。
宇多丸:それで、イート(Eat)・シーンもありましたね。
山本:イート・シーン、あったんですよ!
宇多丸:まず、松浦亜弥さんのそのミュージックビデオを見て……っていう。そこがまず、イート・シーンですもんね。
山本:あそこの、宇多丸さん。おそらく私はのり弁だと踏んでいるんですけども。本当にお米ひとかけらを食べて、その後にもう食事に手が付かないくらい夢中になっちゃうっていうことですよね。あそこのシーンはね。なんか、ああいうのを見ていると……。
宇多丸:あれも冷めきった弁当なんでしょうね。
山本:冷めきった弁当で、もう落ち込んでいて。
宇多丸:弁当も冷めきってるし。あそこでの松坂桃李さんの目も冷めきっている。ちゃんと目に光がなかったところに、涙と共に光が戻ってくる。これ、ちゃんとやりますよね。
山本:そうですね。なんか忘れられない人のあの頃の食事ってあるよなって思い出しました。僕は。
宇多丸:そうね。だからその弁当と対照的にですよ、あったかい方の食べ物もあったじゃないですか。忘れられない、食事っていう意味では。
山本:ありましたよ、シチュー! ホワイトですよ!
宇多丸:ねえ。ホワイトシチュー。
山本:ホワイトですよ! そこからまた、いい風に転がっていくわけですよね。光が差してくると言いますか。
宇多丸:あれもやっぱりさ、決して褒められたもんじゃない人っていうのと同じく、別にうまいわけじゃないっていうか、むしろマズい味っていうのとセットで、その人とかその瞬間のことを覚えてる、みたいな。で、それ自体がやっぱりなんていうか、いいとか悪いじゃなくて、もう、「そういう道を歩んできたんだな」っていう時間だったりしてね。
山本:また、あの仲野太賀さんが演じるキャラクターの性格上、そのキャラクターが作ったホワイトシチューじゃないですか。で、なんかそのキャラクターと、そのキャラクターが作ったホワイトシチューのざらつきみたいな。ざらついてるんだ……みたいな。そこのリンクっていうか。
宇多丸:「なんか粉っぽいんですけど」みたいな。
山本:その不器用っぽいところもそうなんですよね。なんかあそこもたまらなかったですよね。
宇多丸:モデルになったコツリンさんはすごく料理に自信があるってことで、ちょいちょい料理を振る舞ったりはしてたらしいんですけどね。
山本:ああ、そうですか。そうなんだ。
宇多丸:そうそう。まあ、そんなこんなでちょっと後ほど、映画の話は中でするんだけども。その中で描かれている……舞台としてはだいたい2004年から2005年ぐらいにかけてのモーヲタとしての盛り上がり、シーンとその後、みたいな感じじゃないですか。2006年ぐらいまでの。で、ちょっとそのあたりの話をしておくと、まず山本さんってその頃はおいくつぐらいですか?
山本:僕は中学生ぐらいにモーニング娘。の皆さんのオーディション番組『ASAYAN』がやっていたっていう。
宇多丸:それって、見たりしていました? 話題になっていました?
山本:なっていましたなっていました。もう、みんな盛り上がってましたよ。「『ASAYAN』で誰が受かるんだ? 受かった! デビュー曲『モーニングコーヒー』だ! なっちだ!」って言って。
宇多丸:そもそもね、シャ乱Q女性ロックボーカリストオーディションで平家みちよさんが優勝されるんですが、それで落ちた人たちが集められて作られたのが、モーニング娘。でね。要するに、最初からある種、「負け犬たちのワンスアゲイン」的な物語性があって。なおかつ、実はモーニング娘。って、アイドルらしからぬ……もう実はその90年代いっぱい、アイドル冬の時代で。もう僕ら自身も「絶対にアイドルがもう1回盛り上がるなんてことはあり得ないだろう」という空気感の中で。あるとしても、また違う形……たとえばアクターズスクール的なスキル中心主義的だったり、グローバルな形のアイドルだったらあり得るけども、昔ながらの日本アイドルなんてもう無理っしょ?って思ってたんだけど。
モーニング娘。はそういう意味では、安倍なつみさんはいわゆる本当に正統派アイドルイズムだけど、それ以外のメンバーはどっちかっていうと、年齢的に言ってもキャラクター的に言っても、本来で言えばアイドル的ではない人たちっていうのを、ある種メタ的にアイドルに仕立てたのが、『モーニングコーヒー』までのモーニング娘。で。そこから先、つんくさんがまた本格的にプロデュースに乗り出すにあたって、彼のすごく好きなダンスミュージックの要素であるとか……それですごく優れたアレンジャーと組むことで、もう本当にマジックが起こって、っていうあたりで盛り上がってきて。
でも、90年代いっぱいはそれでもやっぱりある意味、ちょっとB級感を背負ったグループとしていて。たとえば鈴木亜美さんとの同日発売対決で負けちゃう、みたいな。そういう、今、思えば非常にバラエティ的な勝ち負け演出があった上での、後藤真希さんが加入しての、『LOVEマシーン』、1999年にドーン!って。
山本:まさに「ドーン!」でしたよ。
宇多丸:それで21世紀に向けてガーッとハロプロ全体として盛り上がっていく、みたいなね。4期メンバーが入ったりしてさらに盛り上がりましたけどね。というのがあって。で、いわゆるモーヲタ・シーンっていうのは、普通のアイドルファン……要するに、そのアイドル冬の時代がずっと長く続いていく中で、まずはリアリティショー、『ASAYAN』というテレビ番組を通したリアリティショーで、その各人の人間性であるとか、そこから浮かび上がるグループとしての物語性、そういうところにまず最初は盛り上がったんですよね。なおかつ、楽曲もすごく面白いからっていうので、まあ大人が騒ぎ出したっていうか。そういう感じですかね。「この楽曲はすごくマニアックだ!」っていう感じですごく騒いだりとか。
で、『ASAYAN』ですごく盛り上がっていた時期があったんだけども、『LOVEマシーン』でブレイクして、プッチモニが出て、ぐらいかな? その4期メンが入る手前ぐらいのところまでで、『ASAYAN』で逐一全てを見せる、みたいなのが、一旦終わるんですよね。まあ、いろんなこと、大人の事情があったんでしょうけど。『ASAYAN』がそのモーニング娘。の主力舞台で、物語性を見せる、っていうところがなくなって。で、それによって、その欠落を埋めるが如く、ちょうどそのインターネット浸透期とかいろいろ重なったっていうのもあって、まあ2ちゃんねるとかそういうところ、そして雑誌で言えばやっぱり『BUBKA』ですよね。とかを中心に、その『ASAYAN』がいろいろ提供していた物語性っていうのを、ファンたちがもう、自分たちで補完するしかない。
曲が出たりとか、いろんな番組とか、いろんな情報の断片をつなぎ合わせて……もうゴシップから何から全部をつなぎ合わせて、「俺たちが物語を補完する」みたいな。っていうので盛り上がったのが、初期モーヲタシーン、っていうことだと思うんですね。もちろんその中には、いろんなフェイズの差があって。単純にメンバーそれぞれがすごく好きで……っていう人もいれば、俺とかは野球チームを応援するようにっていうか、プロ野球のチーム、たとえば巨人軍のファンで、「でも、今回のこの登用はどうなんですか? これ、ちょっと人選ミスなんじゃないですか? これは采配ミスでしょう」とか「この試合運びはなんなんだ?」とか、「ここには、あそこの○○というポジションにはあいつをつけるべきだ!」とか、そういうことを議論して楽しむ、みたいなのもあったりとか。
もちろん、楽曲研究があったりとか。たとえば当時だったら、当時アレンジをしていた人にインタビューしに行ったりして。それをまた、イベントでなんかやったりとかっていう。だから、わりとモーニングとかを、もちろんライブに行ってワーッて盛り上がったりもするけども、終わった後にみんなで飲みながら、なぜか俺たちがそのライブの反省会をする、みたいな(笑)。で、「あそこの使いみちが……まだちょっと5期メンの使いみちがうまくわかってないんじゃないか?」とか、「後藤のソロはどうやったらもっと輝くんだろうか?」とか。勝手に、余計なお世話だ!みたいなことを(笑)ワーワーやって盛り上がる、みたいな。
そこでやっぱり、いろんな人が出会って。たとえば、やっぱりモーニング娘。から、今までアイドルファンとかになったことがなかった人が、そこから狂っちゃった人もいるし。あとは、ずっと昔は好きだったけど、アイドル冬の時代の間はファンをやめていたけども、また復活した、みたいな人もいるし、っていう感じで。そこでいろんな人とどんどん知り合って。たとえば、そうですね。コンバットRECなんかもまさにそうで。掟ポルシェさんもそうだし。吉田豪さんもそういう流れで知り合った人だし。コンバットRECはあれですよね、僕らがいつも語り草にしている清里でのハロコン、清里の高原でやったハロー!プロジェクトのコンサートがあって(2001年9月)。
そこにみんなでバスを借り切って、前日朝までトークイベントをやった後に、みんなでバスを貸し切りにして行くわけですよ。それで俺は前日、大阪でRHYMESTERのライブだったんですよ。大阪のライブが終わった後に、その日に限って楽屋とかにすごく女の子がいっぱいいて、みたいな時に、「あ、俺、帰ります。明日、ちょっと清里があるんで」って。それで女の子は「はあ? 何? 生身の女とモーニング娘。のどっちがいいわけ?」「(即答で)モーニング娘。!」っつって。
山本:フハハハハハハハハッ! オタクの方だ(笑)。
宇多丸:あと「仲間たちが待っているから」みたいなかっこいいことを言って。その待ち合わせているバスに乗って行って。その時の打ち上げとかでRECとかとはすごい仲良くなった気がするな。意気投合して、みたいな。それ以来、すごく会ったりするようになったんですね。なんだけど、この今回の劇中で描かれる2004年というのは、だからそういう意味では、僕らがモーニング娘。ですごく最高潮に盛り上がってた時期の、結構後期っていうか。なんかその楽曲とかに関しては……いろいろあったんですよ。「ハローマゲドン」と呼ばれる……僕らが勝手に呼んでいるんだけどね。ハローマゲドンと言われる、大きな人員の異動っていうか、我々からすると非情にすぎる異動みたいなのがあって。
山本:アルマゲドンにかけているんですね。
宇多丸:ハローマゲドンと呼ばれることがあったりとか、いろんなことがあって……いろいろと、楽曲的にもちょっと乗りきれないものが増えてきたりとかで。2004年の頃、要するに劔さんがハマった時は既に、結構後期で。劇中でね、2005年の場面として描かれる、石川梨華さんの卒業コンサートっていうのが出てきますね? 実はやっぱりあの前後、いろいろあって。早い話が、矢口真里さんが写真週刊誌に……しかも小栗旬さんとの写真を撮られて。それで即日、強制脱退、みたいになっちゃって。
まあ、その処遇に対する意見の違いで、もう僕らの周りだけでも、モーヲタ論壇が真っ二つになっちゃって。真っ二つというか、もっとかな? 本当に内ゲバみたいな感じですよね。それで僕らは、「矢口さんが自分の幸せを選ぶことの何が悪いんだよ? 小栗くんって結構受け答えもしっかりしてるし、いいじゃないか!」なんて言って。それで「矢口を守れキャンペーン」とか「矢口に謝れ」キャンペーンみたいなことをして。その石川さんの卒業コンサート、日本武道館。我々もあそこにいましたよ。で、コンバットRECと矢口キャップをかぶって乗り込んで。
そしたら、その杉作J太郎さんが「いや、それは気持ちはわかるけども、宇多丸さんたち。でも、梨華っちの卒業をちゃんと、気持ちよく送り出すってことはできないんですか、あんたらは?」って言われて。それで、杉作さんは杉作さんで俺たちに怒っていたりとか。で、その「杉作さんが怒っている」っていう情報をまた俺が……それがまたネットですぐに伝わっちゃって。「杉作さん、僕のことを殺すらしいですね?」とかね(笑)。
山本:ええっ? そんな怖い言葉で?
宇多丸:とにかくそんな感じでね、でもそのぐらい熱くなってた、っていう。でも、それを境に、やっぱりいろいろちょっとこう……言っちゃえば初期モーヲタ文化っていうのは、そこで一区切り、みたいになって。なので、今回の劇中ではそこまで細かい事情とかは描かれてないけど、やっぱり石川梨華さんの卒業コンサートを境に、いろんな熱量とか、いろんなことがちょっと変わっていく感じ、みたいなのは、実はさりげなくもニュアンスとしては描かれていて。そうなんです。でも、とにかくひとつ言えるのはですね、六本木ヒルズのスクリーンで、劔さんとかロビンさんとかの話を見る日が来るとは思いませんでした!っていうね。
「どういう気持ちになれと?」っていうね(笑)。本当に、『花束みたいな恋をした』は「(登場人物たちが)頭に住みついてしまった」って言ったけど、(こちらは)元々知っている人たちなんですけど!みたいな(笑)。元々知ってる人たちの……でも俺、ロビンさんとかは、要するに赤犬っていうバンドがいて、赤犬のメンバーとしても知り合いだったんだけど、親しくなるちょっと前の話なんでね。だから、そう。「こんなことやってたの? ひどいね!」っていう(笑)。ちょっとあきれ返るところもあったりしましたけども(笑)。
山本:のぞいてみたらひどかった(笑)。
宇多丸:ひどかった、みたいなのはありますけどね。非常に貴重なっていうか、私個人としても貴重な映画体験でした。「どういう気持ちになれと?」みたいなところもありましたけどね。どんな作品なのかといったあたりはこの後、ムービーウォッチメンで扱いたいと思います。もう19分経っちゃった。こんな話、無限にできるよ(笑)。
【補足2】コーナー直前のCM前にて
宇多丸:……はい。じゃあちょっと残る時間を使って、できるだけ『あの頃。』情報というか、評に入り切らない部分もやっていきたいと思うんですけども。たとえば、びっくりというか、「ああっ!」って思ったのはね、あの学園祭で、意気込んでイベントをやるところがあるじゃないですか。で、意気込んでやった結果、傍から見たらドン引きの光景が現出しちゃって。やっぱりあの頃、いわゆるヲタ芸みたいなのが確立期で。それを象徴する曲が、藤本美貴さんの『ロマンティック浮かれモード』で。特に、サビになると(飛びはねながら頭上で手拍子しつつ)「回る」っていうね。僕らの頃は「マワリ」って言っていたけども。
あれが……でも、主人公たちのチームは、ヲタ芸を積極的に打つ側じゃない。だからそのヲタの中でも、打つ派と打たない派もいるし。でも、やっぱりみんながワーッてなっているのを見ると高揚してしまう、あの感じとかもすごくわかる……だけにちょっと、当時の自分たちを思い出すようで、頭を抱えちゃうようなところもあったし(笑)。スクリーンを見ていて、恥ずかしくてこう、頭を抱えて(笑)。
あと、この間もRECもちょっと話題にしていましたけども。「サムライ」と呼ばれる……本名は別にあるんだけども、サムライさんと呼ばれる、チョンマゲにした長身の、当時の有名ヲタなんですね。我々の友人なんですけども。友人でかつ、いろんな問題がある人なんですけども(笑)。そのサムライさんの当時していた格好。赤いつなぎに、アフリカ・バンバータがしているような細長いグラサンをして。なおかつ、俺が、風体のみならずびっくりしたのは、サムライさんの踊り方がもう、完コピなんですよ。ヲタ芸じゃなくてね。ヲタ芸を周りでやっているのに、すごい自由な……。
山本:あっ、あの人ですか? サングラスの?
宇多丸:フニャフニャフニャフニャ、独自の踊り方をしているんだけども。あ、今、本名を言いそうになったけども(笑)、「あっ、サムライさんの踊り方だ! えっ、これ、どうやってコピーしたの?」みたいな。
山本:あの髪の長い人ですよね?
宇多丸:そうですそうです。あれ、本当にそのまんま。
山本:そうなんだ。周りと違って異質な感じでしたもんね。
宇多丸:はい。いろんな意味で、良くも悪くも我が道を行きすぎる人なんですけども。それとかもびっくりしましたしね。で、だからそういう、当時の自分たちを見るようだなっていう場面も当然、あったし。あと、でも一方ではやっぱり、年齢とか立場の差もあるのかな? 東京でモーヲタ・シーンとかにいていろいろやっていたけども、ああいう男子中学生ノリでキャッキャ、みたいなこととも、俺らはちょっと違ったよね。
山本:ああ、そうなんですね。
宇多丸:そうそう。だからあんな、一緒にお風呂に入るとかは絶対にないよ。あ、ちなみにそういう風にやっていた人もいるかもしれないけども。たとえば俺とコンバットRECがやるかって言ったら、絶対にやらない。ただ、RECの家に入り浸って、新譜なんかを聞いたりとか、その入り浸り感は同じなんだけども。ノリは……だからたぶん俺らはもうちょっと大人で、お金もあったし、というところが違うのかもしれないですね。ただ、大人でお金もあって社会人だからこそできる、たとえばその、モーニングとかのインサイダー情報がそれなりに入ってくる、みたいな(笑)。
山本:インサイダー情報? モーニング娘。の?(笑)。
宇多丸:一応、音楽業界にいるし……みたいな(笑)。
山本:すごい生々しいですね(笑)。
宇多丸:そういう、社会的地位があるなりのダメさ、みたいな(笑)。とか、ラジオ局の……「これ、後藤さんが残していった落書きの団扇なんですよ」みたいな。「ごっちんが書いた落書き? ください!」みたいな(笑)。今日、持ってくればよかったな(笑)。そんなこんなで、この後はムービーウォッチメン『あの頃。』です。
(ガチャ回しパート中略 ~ 来週の課題映画は『DAU. ナターシャ』です)

以上、「誰が映画を見張るのか?」 週刊映画時評ムービーウォッチメンのコーナーでした。